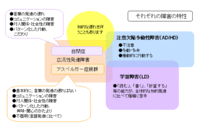発達障害
知的、発達障がい者の行動と目的①
知的障がいを持つ方や、発達障がいを持つ方によく見られる問題行動の主な機能(目的)について考えてみましょう。
1つ目は、『事物の獲得』であり、食べ物や玩具などを手に入れることを目的とした行動です。
2つ目は、『課題からの逃避』であり、課題や作業を中断したい、作業を止めたいということを目的とした行動です。
3つ目は、『注意の獲得』であり、他者の注意を得ることを目的とした行動です。
4つ目は、『感覚刺激を得る』であり、先の3つの機能に当てはまらない行動は自己刺激を得ることを目的とした行動と考えられます。
発達障害のある人たちが示す問題行動のほとんどは、上記の4つのいずれかの機能、または、複数の機能を持ち、これらの要求が通ることで形成、維持されます。
つまり、(A)ある状況で(B)ある行動を行い(C)上記のいずれかの要求が通る、または好ましい感覚が得られる、ということを経験すると、その状況(A)でその行動(B)が出現しやすくなり、習慣となっていくということです。
A(先行条件) ➡ B(行動) ➡ C(結果)
いつもこの順序で分析することが重要となります。
注意するのは、行動の形態は同じであっても機能(目的)が異なることがあるということです。
2つのケースを例に挙げて考えると
ケース1:「(A)お菓子売り場に母親といる→(B)頭を叩く→(C)お菓子を買ってもらう」の(B)頭を叩くは事物の獲得の機能を持っている
ケース2:「(A)作業を行っている→(B)頭を叩く→(C)作業が中断される」の(B)頭を叩くは課題からの逃避の機能を持っていると推測できます。
このことからも行動の形態や行動そのものに注目するのではなく、
前後関係から機能を推測するによって、有効な支援計画を立てることができることが分かります。

1つ目は、『事物の獲得』であり、食べ物や玩具などを手に入れることを目的とした行動です。
2つ目は、『課題からの逃避』であり、課題や作業を中断したい、作業を止めたいということを目的とした行動です。
3つ目は、『注意の獲得』であり、他者の注意を得ることを目的とした行動です。
4つ目は、『感覚刺激を得る』であり、先の3つの機能に当てはまらない行動は自己刺激を得ることを目的とした行動と考えられます。
発達障害のある人たちが示す問題行動のほとんどは、上記の4つのいずれかの機能、または、複数の機能を持ち、これらの要求が通ることで形成、維持されます。
つまり、(A)ある状況で(B)ある行動を行い(C)上記のいずれかの要求が通る、または好ましい感覚が得られる、ということを経験すると、その状況(A)でその行動(B)が出現しやすくなり、習慣となっていくということです。
A(先行条件) ➡ B(行動) ➡ C(結果)
いつもこの順序で分析することが重要となります。
注意するのは、行動の形態は同じであっても機能(目的)が異なることがあるということです。
2つのケースを例に挙げて考えると
ケース1:「(A)お菓子売り場に母親といる→(B)頭を叩く→(C)お菓子を買ってもらう」の(B)頭を叩くは事物の獲得の機能を持っている
ケース2:「(A)作業を行っている→(B)頭を叩く→(C)作業が中断される」の(B)頭を叩くは課題からの逃避の機能を持っていると推測できます。
このことからも行動の形態や行動そのものに注目するのではなく、
前後関係から機能を推測するによって、有効な支援計画を立てることができることが分かります。