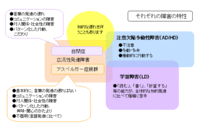発達障害
発達障がいの方とのコミュニケーション①
「発達障害」は「見えにくい障害」とも呼ばれることもあります。発達的には遅れや偏りがわずかであったり、部分的であったりすることから、日常生活を送る上では「障害」と思われにくく、「ふざけている」「本人の努力不足」「親のしつけがなっていない」などの誤解を受けやすいのです。このような「見えにくい障害」を抱えた方々と、よりよいコミュニケーションを図るための工夫をまとめると。
①個別に働きかける
「○○さん」と呼名するだけでも、その人の意識を向けやすくなります。できれば近くで働きかけるほうが、より伝わりやすいでしょう。
②一文を短く、明瞭な声で、はっきりと話す
だらだらとした長い文章よりも、「○○は△△です」「**をしてください」と内容ごとに文を短く区切ると分かりやすくなります。複数の内容があるときには「1番は○○です」「2番は△△です」と番号をつけると、より明確になるでしょう。
③重要なこと、伝えたいことをボードや紙に書いて視覚的に提示する
聞くだけでなく目で見ることによって、より情報が伝わりやすくなります。手順なども順番を明確に図にするのが良いです。
④明瞭に言葉にする
「○○してほしいんだけど・・・」のような言い方でなく、「△△のときは○○してくださいね」と、伝えたい内容を明確にした表現の方がはっきり意図が伝わります。また、日本語の会話の中では、よく、主語を省いたり、内容を省略して話すことがありますが、文脈の中で相手の意図を読み取らなければならないため、すれ違いが起こったりすることもあります。
⑤「ついたて」などで余計な視覚的情報を防ぐ
逆に、視覚的な情報が入りやすいために、周囲に余計な刺激があると、集中が途切れたり、興味関心のある物の方に意識が向いてしまうこともあります。

次回へ続く
①個別に働きかける
「○○さん」と呼名するだけでも、その人の意識を向けやすくなります。できれば近くで働きかけるほうが、より伝わりやすいでしょう。
②一文を短く、明瞭な声で、はっきりと話す
だらだらとした長い文章よりも、「○○は△△です」「**をしてください」と内容ごとに文を短く区切ると分かりやすくなります。複数の内容があるときには「1番は○○です」「2番は△△です」と番号をつけると、より明確になるでしょう。
③重要なこと、伝えたいことをボードや紙に書いて視覚的に提示する
聞くだけでなく目で見ることによって、より情報が伝わりやすくなります。手順なども順番を明確に図にするのが良いです。
④明瞭に言葉にする
「○○してほしいんだけど・・・」のような言い方でなく、「△△のときは○○してくださいね」と、伝えたい内容を明確にした表現の方がはっきり意図が伝わります。また、日本語の会話の中では、よく、主語を省いたり、内容を省略して話すことがありますが、文脈の中で相手の意図を読み取らなければならないため、すれ違いが起こったりすることもあります。
⑤「ついたて」などで余計な視覚的情報を防ぐ
逆に、視覚的な情報が入りやすいために、周囲に余計な刺激があると、集中が途切れたり、興味関心のある物の方に意識が向いてしまうこともあります。

次回へ続く